プロバイダ責任制限法とは|開示請求できるもの等わかりやすく解説
プロバイダ責任制限法とはどのような法律なのでしょうか?今回は、ネット社会で自分を守るために知っておきたいプロバイダ責…[続きを読む]
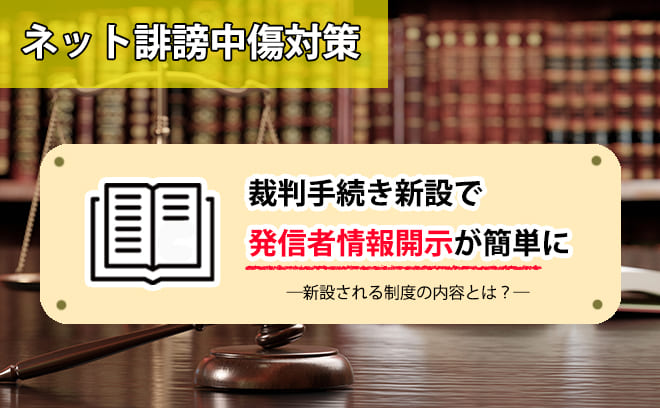
目次
2021年4月25日に、プロバイダ責任制限法の改正法*が参議院にて全会一致で可決されました。
*4月28日公布。正式名称「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」)
施行はいつからかといいますと、それまで明確な施工日は決まっていませんでしたが、以下の通り決定致しました。
そして、新制度の実施に必要な総務省令や最高裁判所規則などが次々と制定され、新しい制度の具体的な手続等が整備されることが予想されます。
今回の主な改正点は、わかりやすく結論から言いますと下記の2点です。
プロバイダ責任制限法は、インターネット上での誹謗中傷など他人の権利を侵害する「権利侵害情報」を投稿した者(以下、発信者と言います)の住所氏名などの情報が「開示」されるための要件等を定めた法律です。
ただ、手続の迅速化と、従来の規定では開示が認められない類型への対応など問題点があり、かねてから改正を強く望まれていました。
今回の改正はこの点に対応するものであり、いつからなのかと多くの人が期待しており、プロバイダ責任制限法制定以来の大改正であると言われています。
なお、プロパイダ責任制限法の概要については下記の記事がわかりやすいのでご参考ください。
犯罪を構成するようなネット上で行われる誹謗中傷等の言動は、近時ますます大きな社会問題となっています。
このような誹謗中傷等の被害を受けた場合、最終的には不法行為に基づく損害賠償請求の訴訟等によって解決することになりますが、このような賠償請求は、加害者である発信者の住所氏名などの情報が分からなければ有効な解決に至ることはありません。
そのために従来から、プロバイダ責任制限法に定められた発信者情報開示請求の制度がありました。
改正の背景を解説します。従前の制度は、2段階の裁判手続が必要であることから、発信者の個人情報を入手するまでに多くの時間と手間がかかり、その間に発信者の記録が失われる場合もあることから、被害者保護の観点からデメリット・問題が指摘されていました。
また、特に海外のコンテンツプロバイダ(掲示版やSNS等の運営業者)に多いのですが、コンテンツプロバイダの中には、個別の投稿に関するユーザーの情報(従来の発信者情報)を保有せず、投稿の前後に行うログイン及びログアウト時の情報しか保有していない業者があります。
このようなログインのための通信に関する情報は、従来の制度で開示が認められていた権利侵害を発生させる通信に関する情報そのものではないため、その開示が認められるかどうかの議論があり、条文解釈では対応しきれないという問題点が指摘されていました。
今回の2022年の改正をわかりやすく言うと、主にこの2点がきっかけとなり、問題点に対応したものであり、これによって被害者が発信者情報を入手して被害回復をよりスムーズに行えるようにするものです。
従来の制度において、発信者の個人情報を入手するためには、まず掲示版やSNSの運営業者などのコンテンツプロバイダに対して、発信者のIPアドレス等の情報の開示を求める仮処分等の手続を行います。
その上で、これによって開示を受けた発信者のIPアドレス等から判明したアクセスプロバイダに対して改めて訴訟により発信者の住所氏名などの情報の開示を請求する必要がありました。
今回の改正は、このような2段階の手続はありません。
一つの裁判手続の中で、コンテンツプロバイダに対する発信者IPアドレス等の情報開示と、これによって判明するアクセスプロバイダに対する発信者の住所氏名等の情報の開示手続きを行う制度を創設するものです。
これにより、被害者の手続の負担が軽減され、わかりやすくなり、開示までにかかる時間も短縮されることが期待されています。
新しい制度では、以下の3つの命令が新設されます。
発信者情報の開示をプロバイダに対して命じる大本の手続です。
開示を求める被害者(申立人)は、裁判所に対してこの命令の発令を求める申し立てをすることになります。
提供命令には以下の2つの命令があります。
・1号命令
申立人に対し、コンテンツプロバイダからアクセスプロバイダの情報を提供することを命じる命令
・2号命令
1号の提供命令により特定できたアクセスプロバイダに対して、コンテンツプロバイダの保有する発信者情報を提供することを命じる命令
提供命令の要件は、いずれも現行法での発信者情報開示の要件と比較してかなり緩和されています。
つまり、早期に発信者の住所氏名等の情報を保有するアクセスプロバイダを特定することが可能となりました。
これまで情報保全のため別途なされていた仮処分申立てに代わる制度であり、開示請求の対象となっている発信者情報の消去を禁ずる命令を、同じ発信者情報開示命令手続の中で発することができるようになります。
当該発信者情報開示命令事件が終了するまでの間、発信者情報を保有するプロバイダは当該情報の消去を禁じられるため、被害者が発信者情報の開示を受けるまで情報が保全されます。
なお、新しい裁判制度は、訴訟手続よりも簡易な非訟事件という裁判手続でなされることになっています。
また、これまで必要だった副本の送達(プロバイダに対する裁判に関する書面の正式な送付方法)に代わる「申立書の写しの送付(新11条)」という新たな制度が設けられます。
特にコンテンツプロバイダに多い海外法人を相手取る場合、改正前よりも柔軟かつ迅速な手続の進行が期待されます。
また、X(旧 ツイッター)やグーグルなど、近年のネットサービスはユーザーがログインをした上で、情報を書き込む方式が増えています。これらのサービスの中には、ユーザーの書き込み時のIPアドレスを保有せず、ログインとログアウトの際のIPアドレスのみを保有している業者が多くあります。
従来の発信者情報開示請求では、開示を請求できるのが権利侵害を発生させる通信そのものの情報に限られていたため、ログインとログアウトのための通信に関する情報しか保有しないコンテンツプロバイダに対して、どのようにして加害者が接続したアクセスプロバイダを特定するための情報開示を認めるか、法解釈の工夫が試みられていました。
しかし、発信者情報という言葉の拡大解釈でログイン情報の開示を認めたり、ログイン通信を媒介していれば権利侵害通信も媒介したであろうという経験則による事実認定といった条文解釈の工夫には限界がありました。
そのため裁判所の見解も分かれ、ログイン情報しか持たないコンテンツプロバイダに対する発信者情報開示が否定される事例も多数ありました。
そこで今回の法改正により、このようなログイン通信に関する情報についても、要件を厳しくしつつ、侵害関連通信として正面から発信者情報開示の対象とすることが規定されました(新5条3項)。
この改正により、従来「発信者情報開示請求が認められなかったケース」でも、開示が認められるようになることが期待されています。
今回はプロバイダ責任制限法の改正の施行はいつからか、デメリットや問題点など解説しつつ、発信者情報開示の制度はわかりやすく大きく変わったことを解説しました。
しかし、改正された条文からだけでは、具体的な手続の詳細がまだ明確でないところが多く、例えば「有名なあのコンテンツプロバイダに対する発信者情報開示は可能なの?」といった問題提起が数多く専門家からなされているのが現状であり、その点はデメリット・問題点と言えるでしょう。
また、今回の改正後も、従来の仮処分と訴訟の二段階による発信者情報開示請求も認められると考えられていますが、今回新設された新しい裁判制度と従来の制度との関係については、十分明らかになっていません。
具体的な手続の詳細は、今後制定される総務省令や最高裁判所規則によって、詳細が定められることになり、具体的な省令の定め方次第で、発信者情報開示の制度がこれまでよりもうまく機能するのかが決まります。
また、新しいサービスが日々生まれているインターネットの世界で、すでに今回の改正時点で法律がどこまで現状に対応できるのかがすでに議論されており、今後の変化にどれだけ対応して被害者の実効的な救済を図っていけるのか、課題・デメリットも多くあります。
なお、今回の改正が成立する際の附帯決議として、事業者向けガイドラインの作成や、被害者支援制度の充実、児童生徒に対する情報モラルやICTリテラシー教育の充実、発信者情報開示手続等に関する国際協力体制構築などが盛り込まれてもいます。
今回は、プロバイダ責任制限法の改正また施行日が2022年10月1日に決定されたことや内容、課題、デメリット、問題点などをわかりやすく解説しました。
法制度によって情報通信技術の発達が無用に阻害されることは好ましいことではありません。また、発信者情報開示制度の設計にあたっては、常に発信者の表現の自由や通信の自由と、表現行為により権利を侵害された人の救済との間の繊細なバランスをとることが求められています。
その中で今回の法改正による新しい制度がうまく機能し、被害者の保護を拡充できるかは、発信者情報開示を受けるプロバイダ側の協力次第という面が否定できないこと、特に巨大な海外企業の動向が注目されるとの指摘が専門家からなされています。
私たちは、表現者である一方でいつでも被害者になり得ることを念頭に、情報通信サービスの消費者としても常に注意深く、今後の制度運用の状況を見守っていく必要があると言えます。