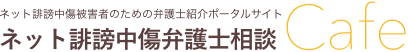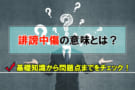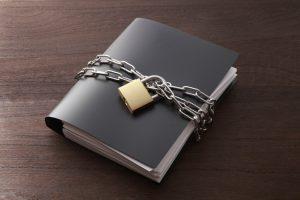近所や職場で悪口や噂を流された! 名誉毀損で慰謝料は請求できる?
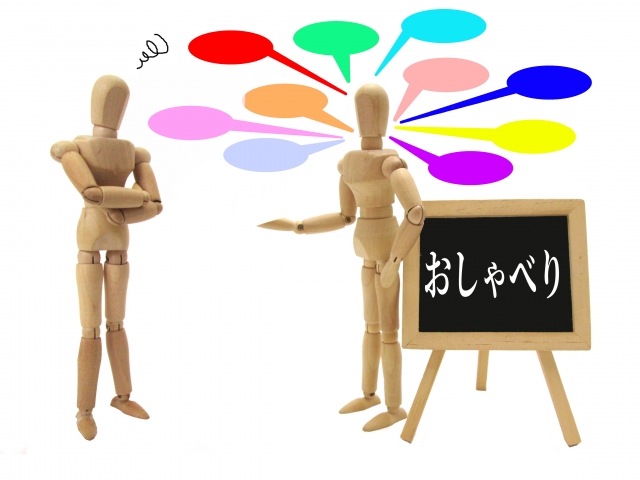
最近では、インターネット上での誹謗中傷につき、名誉毀損を理由に慰謝料を請求する例が増えています。
ただ、慰謝料請求が認められるのは、インターネット上での誹謗中傷だけではありません。
近所や職場など、現実世界で悪口を言いふらされた場合などにも、加害者に慰謝料を請求できます。
今回は、近所や職場など現実世界における誹謗中傷などについて、慰謝料請求の要件や注意点などを解説します。
目次
名誉毀損とは
名誉毀損とは、誹謗中傷などの言動によって、他人の社会的評価を下げたり、名誉感情を害したりすることをいいます。
表現行為については、原則として表現の自由が認められています(日本国憲法21条1項)。
しかし、正当な理由がない身勝手な放言によって他人を傷つけることは、公共の福祉に反する行為です(日本国憲法13条)。
そのため、名誉毀損に当たる言動をした人は、刑事・民事上の法的責任を負うものとされています。
名誉毀損をした人が負う法的責任
名誉毀損に当たる言動をした人は、名誉毀損罪による刑事責任と、被害者に対する損害賠償責任を負います。
名誉毀損罪による刑事責任
刑法230条1項では、他人の社会的評価を下げる言動を処罰する「名誉毀損罪」が定められています。名誉毀損罪が成立するのは、以下の要件をすべて満たす場合です。
(1)公然と発言がなされたこと
「公然」とは、不特定または多数の人に伝わる可能性のある状態です。たとえば、公衆の面前で行われる発言は「公然」となされたものに当たります。
(2)発言の中で事実を摘示したこと
何らかの事実を摘示した上での発言であることが、名誉毀損罪の要件です。事実の摘示がない場合は、侮辱罪(刑法231条)が成立します。
(3)他人の名誉を毀損したこと
「名誉を毀損」するとは、被害者の社会的評価を下げるような発言をすることを意味します。なお、実際に被害者の社会的評価が下がっていなくても、そのおそれがあれば足ります。
(4)公共の利害に関する場合の特例に該当しないこと
(1)から(3)を満たしていても、以下のすべての要件を満たす場合には、例外的に名誉毀損罪が成立しません(刑法230条の2第1項)。
- 言動が公共の利害に関する事実に関係すること
- 言動の目的が専ら公益を図ることにあったと認められること
- 摘示された事実が真実であることの証明があったこと
(5)犯罪の故意があること
発言の中で摘示した事実が真実でなかった場合に、誤信について確実な資料・根拠に照らして相当の理由があるときは、犯罪の故意がないものとして名誉毀損罪は成立しません(最高裁昭和44年6月25日判決)。
名誉毀損罪の法定刑は「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」です。被害者は、名誉毀損をした加害者を刑事告訴することができます。
被害者に対する損害賠償責任
誹謗中傷などの発言をした加害者は、被害者に対して不法行為に基づく損害賠償責任を負います(民法709条)。
民法上の不法行為は、刑法上の名誉毀損罪とは異なり、被害者の社会的評価を下げる言動に限らず、名誉感情を害する言動についても成立する可能性があります。損害賠償請求(慰謝料請求)の具体的な要件については、次の項目で詳しく見ていきましょう。
名誉毀損で慰謝料を請求するための要件
近所や職場での悪口などについて、加害者に慰謝料を請求するための要件は、以下のとおりです。
- (1)加害者の故意または過失
- (2)言動の違法性
- (3)損害の発生
加害者の故意または過失
慰謝料請求が認められるためには、加害者の発言について故意または過失があることが必要です。
被害者の社会的評価を下げる発言や、名誉感情を害する発言をしたのであれば、大抵の場合は加害者の故意または過失が認められます。
ただし、発言について何らかの誤解があり、誤解について確実な資料・根拠に照らして相当の理由があるときなどには、加害者の故意・過失が否定される可能性があると考えられます。
発言の違法性
不法行為の成立には、問題となる発言が違法であることが必要です。
被害者の社会的評価を下げる発言や、名誉感情を害する発言は、原則として違法性が認められます。ただし、公共の利害に関する場合の特例(刑法230条の2)に該当する場合は、名誉毀損罪に準じて違法性が阻却されると解されています。
- <公共の利害に関する場合の特例の要件>
- ・言動が公共の利害に関する事実に関係すること
- ・言動の目的が専ら公益を図ることにあったと認められること
- ・摘示された事実が真実であることの証明があったこと
また、何らかの事実を前提とした意見・論評については、前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があれば、違法性が阻却されます(最高裁平成9年9月9日判決)。
損害の発生
不法行為に基づく損害賠償請求は、被害者に生じた損害を金銭に換算した額について認められます。
悪口などについて慰謝料請求を行う被害者は、自身に生じた精神的損害が、どの程度の金銭的価値に相当するのかを主張・立証しなければなりません。
具体的には、加害者の発言内容のひどさ・しつこさ、被害者が精神疾患を患った場合にはその症状などを主張することになります。慰謝料の金額相場については、後述します。
名誉毀損による慰謝料請求には証拠が必要
近所や職場での悪口などにつき、名誉毀損による慰謝料請求を行うに当たっては、不法行為の成立要件を立証する必要があります。そのためには、加害者の発言や被害者が受けた精神的損害についての証拠を集めなければなりません。
加害者の発言についての証拠としては、ボイスレコーダーで録音した音声などを利用できます。また、悪口を聞いたという会社の同僚や近隣住民などの証言が得られれば、有力な証拠となるでしょう。
被害者が受けた精神的損害については、加害者の発言内容やその頻度などが立証できれば、最終的には裁判所が過去の裁判例を参考に見積もってくれます。精神的損害の深刻さをさらに強調したい場合には、精神疾患に関する医師の診断書を提出するなどが有力な方法です。
悪口を言いふらされた場合の慰謝料相場
悪口・誹謗中傷について認められる慰謝料額は、発言内容・頻度・被害者の受けたショックの大きさなどによって異なりますが、おおむね「50万円から200万円程度」となるケースが多いです。
特に、悪口が広範囲の人に伝播した場合には、被害者の社会的評価に与える影響が大きいものとして、高額の慰謝料が認められる可能性があります。また、被害者が深刻な精神疾患を発症した場合にも、慰謝料は高額になる可能性が高いでしょう。
十分な金額の慰謝料を獲得するためには、不法行為の要件に従い、被害者の受けた精神的損害の深刻さを説得的に主張することが大切です。
まとめ
インターネット上のみならず、現実世界で悪口を言いふらされた場合にも、加害者に対して慰謝料を請求できます。
適正な金額の慰謝料を獲得するには、悪口についての証拠を固めた上で、周到に準備を行ってから慰謝料請求を行うことが大切です。そのためには、法律上の要件や過去の裁判例などを踏まえた慎重な検討が求められます。
弁護士は、誹謗中傷などを理由とする慰謝料請求につき、被害者を全面的にサポートいたします。近所や職場でご自身の悪口を言いふらされている方は、一度弁護士までご相談ください。