プライバシーの侵害と肖像権!他人にSNSで勝手に個人画像を載せられた
SNSに写真を勝手に公開され、写っている人たちに迷惑を与える行為は「フォトハラ」とも呼ばれます。他人にSNSで個人画…[続きを読む]
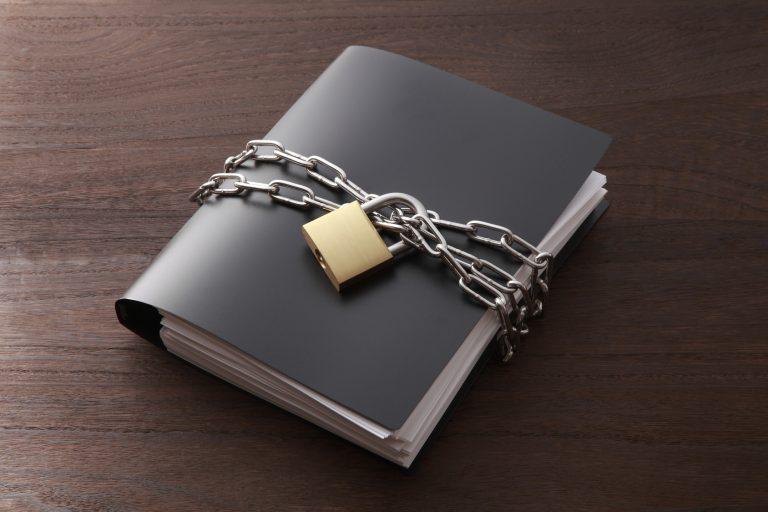
X(旧 ツイッター)などSNS・インターネット上では、匿名の投稿者によって、自分の実名や住所など個人情報が勝手に書き込まれることがあります。
そのような「個人情報の晒し書き込み」は罪ではないのでしょうか?何らかの取り締まる法律はないのでしょうか?
また、晒されたあとのその後の被害を抑えるためにも、できる限り個人情報が書かれた投稿は迅速に削除したいと考えるのが普通でしょう。
そこで今回は、ネット上で人の名前を勝手に載せたり、個人情報を勝手に言いふらしたり教えたりすることはどのような犯罪に当たり、実名や住所の晒し行為・拡散・書き込みや悪用があった場合にどのような対処法があるのか法律などについて解説していきます。
目次
代表的なSNSであるFacebook・Twitter・Instagram、また5ちゃんねる・爆サイなどでは、「実名が晒された」「住所、電話番号が書き込まれた」「個人情報を流された」という被害が後をたちません。
というように、過去の職業や今は隠したい情報をネットに晒し行為にあい、公開されてしまうこともあります。
悪意がなく、プライベートな画像が許可なく投稿されるケースもあります。
このような、悪意のない投稿であっても、これをきっかけにその後トラブルに巻き込まれることがあるのです。
例えば、閲覧者に住所が特定されたり、子どもの氏名や学校などを知られたりすることもあります。
このような投稿を悪用する人もいるため、なるべく投稿や晒しに早く対処したいと考える人も多いでしょう。
そもそも、このような個人情報の漏洩は法的に問題はないのでしょうか。書き込みや特定は罪ではないのでしょうか?個人情報に関する法的な問題について確認してみましょう。
他人の実名・住所・電話番号等をネット上に掲載した場合、「プライバシー権の侵害」が成立し、各種の責任が発生する可能性があります。
プライバシー権は憲法13条で保障される人権の1つであり、「私生活上の情報をみだりに公開されない権利」と定義されています。
この権利は、法律にはっきりと明文化されているわけではありませんが、憲法13条の解釈から認められています。
そのため、プライバシー侵害によって被害を受けた場合には、不法行為による損害賠償請求などが認められる可能性があります。
友人・知人や家族などと一緒に写真を撮影する際、「写真を撮影すること」については了承している場合がほとんどですが、「ブログやSNSなどのネット上にアップする」ことまでは、許可していないことも多いでしょう。
このように、たとえ撮影自体は承諾していても、公表については承諾せずにネット上に画像をアップされた場合、「肖像権の侵害」になります。
肖像権とは、「無断で自分の写真や画像を撮影されたり、無断で公表・利用されたりしないための権利」で、憲法上の権利である人格権の一部として保障されると考えられているものです。
もし肖像権侵害があった場合、プライバシー権同様、民事上の責任(損害賠償)を追及することが可能です。
プライバシーの侵害は、刑法で刑事罰が規定されているわけではありません。
つまり、個人情報を書き込んだだけでは犯罪にはならないのです。
しかし、個人情報の書き込みに加えて、他の犯罪に該当する行為をした場合は刑事責任が問われる可能性もあります。
例えば、氏名・住所といった個人情報と共に「コイツは社内で不倫している」といった書き込みを行いネット上に拡散したとしましょう。
すると、後者の内容は事実を摘示することによって相手の社会的評価を低下させているため、「名誉毀損罪(刑法230条)」が成立する可能性があります。
名誉毀損罪は当然に犯罪であるため、前科がつくと同時に、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金刑に科されるおそれがあります。
以上のように、投稿内容によってはプライバシー侵害以外の犯罪で罰せられる可能性が十分にあります。
それでは、個人情報を勝手に書き込まれたときはどのように対処すればいいのでしょうか。
このとき、サイトの管理者や運営会社に連絡・通報することで個人情報を削除してもらえる可能性があります。
削除依頼の方法としては、以下の2つがあります。
ネットの掲示板やSNSの多くには、問い合わせフォームや削除フォーム、通報ボタンなどが設置されています。
それを利用して「プライバシーが侵害されて被害がでている」と理由を付けて連絡すれば、任意で削除対応をしてくれるケースがあります。
対応方法は各サイトで異なるため、下記記事も併せてご参照ください。
削除フォームがなかったり削除に応じてもらえなかったりした場合、プロバイダ責任制限法という法律に基づいて削除請求をする方法があります。
この方法を「送信防止措置」といいます。
基本的に書面を書いて送付することで削除依頼をすることができます。
ただし、最終的に削除するかどうかはサイト管理者の判断によるため、必ずしも削除されるとは限らないことに注意してください。
上記2つの方法で削除できなかった場合、裁判所に仮処分を申し立てて法的に削除してもらう必要があります。
仮処分では暫定的な判断で投稿の削除が認められるため、通常の訴訟より短期間・低コストで対処することができます。
また、出された仮処分命令には強制力があるため、削除してもらえない心配もありません。
ネット上に個人情報を晒されたとき、ただ投稿を削除するのではなく、犯人に慰謝料(損害賠償)請求をしたいと考える人もいるでしょう。
そのためには、まず投稿者を特定する必要があります。
ネット上の書き込みは匿名で行われていることも多く、すぐ加害者を特定するのは困難です。
このような場合、先ほどのプロバイダ責任制限法を使って、サイトの管理者に対し「発信者情報開示請求」をすることになります。
この手続きによって、相手方の実名・住所・メールアドレス・IPアドレスなどの情報が開示され、匿名相手の特定が可能となります。
相手を特定した後、慰謝料請求訴訟を起こします。
個人情報の書き込みやプライバシーの侵害が行われた場合の慰謝料の相場は、約10~50万円程度と言われています(事業に対する妨害などがあれば50~100万円になることも)。
また、ヌード写真が投稿された場合などの特殊な事情があれば、600万円という高額な慰謝料が認められた例もあります。
そこで、もしネット上のトラブルに関して悩んだときには、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士であれば、上述した投稿の削除・犯人の特定・慰謝料請求の一連の流れを受け持ってくれますし、知識や経験を活かして有利に進めてくれるでしょう。
加えて、一個人が削除請求をすると応じない場合でも、弁護士が連絡すると要求に応じるサイトが多いのもメリットの1つといえます。
法的な問題を扱う際には、弁護士との密なコミュニケーションと、正確な情報提供が非常に重要です。状況によっては、時間と費用がかかる場合もあるため、事前の準備と理解が必要です。
ただ、依頼をするとしても弁護士費用が気になるところ。
最後に、弁護士費用について簡単にご説明していきます。
弁護士費用は、基本的に着手金・報酬金・実費という構成に分けられます。
着手金の相場は、下記のとおりです。
成功報酬金の相場は、下記のとおりです。
なお、実費は書類発行費・交通費・郵送費など、弁護士が依頼をこなす際に必要となる費用です。
そのため、依頼内容によって変わってきます。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
以上が、X(旧Twitter・ツイッター)などで個人情報や実名などが晒されたときの法的な問題や対処法などでした。
ネット上の誰でも見られるところに自分の個人情報が公開されているのは、気分が良いものではありませんよね。
どこで悪用されているのかもわからず、不安になると思います。
もし個人情報晒しで悩んでいるのであれば、多くのサイトやSNSは自分でもできる通報フォームなどが用意されているはずなので、まずはそれを試してみてください。
それでも削除できなかった場合は、弁護士や行政など、専門家に相談してみてはいかがでしょうか。